吉本隆明が亡くなってすぐ、新潮と朝日新聞に、中沢新一が追悼文を書いていて、どちらも読んだ。吉本の言語論に触れたくだり、うなずける部分とうなずけない部分がある。
吉本さんは『言語にとって美とはなにか』以来、言語を「指示表出」と「自己表出」という二つの軸のつくる「複素平面」としてとらえる視点を展開していった。
(「『自然史過程』について」新潮2012年5月号)
「複素平面」が目を引く。言語美にはいろいろ図が入っているけれど、「複素平面」であることを明示したものは見あたらない。括弧でくくられているが、吉本自身がどこかでそう言っているのか。あるいは中沢新一の見たてなのか。どちらにせよ、これは的を射た見方だと思った。たとえば次のような図は、不親切すぎる気がする。

(加藤典洋『テクストから遠く離れて』p.11の「図1」)
吉本の言語論によれば、言語表現の「価値」は、「その自己表出の値Xと指示表出の値Yの相関、関係性としての値」で示される。加藤典洋は、『テクストから遠く離れて』で、そう言っている。その際、掲げていたのが、この図だ。
けれど、この、X軸に自己表出を、Y軸に指示表出をとり、第一象限に「言語A(x,y)」ポツンと置いただけのデカルト平面をいくら眺めても、言語が、自己表出と指示表出の間に、いったいどんな関係を作り上げているのか、そのことが全然わからない。だから、「関係性としての値」と言われても、困ってしまう。
ところが当の言語美では、両表出の関係が、もっとはっきり示されている。こんなふうに。
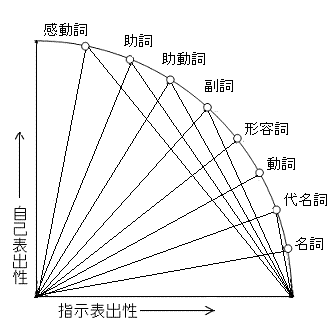
(吉本隆明『定本言語にとって美とはなにかI』p.70の「第4図」)
指示表出性が増加するに伴って、自己表出性が減少する。つまり両表出は、いわゆる「負の相関関係」にあると、吉本は言っているわけだ。
ただし、注意が必要なのは、この散布図が、あくまで語のレベルでの両表出の関係を示したものにすぎないということだ。
言語美で、吉本は、人間の言語を、いくつかの階層に分けて考えている。語のレベルは、吉本の体系で、その最下層に位置づけられる。だから、複数の語から構成された文をとって見た場合、その文の指示表出性と自己表出性が、語と同様の「負の相関関係」になければならないと言っているわけではない。また、個々の文が積み重なって一個の文学作品を構築するとき、二つの表出のそれぞれのとる値が、全体として「負の相関関係」にあるとも言っていない。このあたり、これまでの吉本論で、よく意識されていないところだ。
吉本によれば、言語表現は「指示表出と自己表出の織物」(『定本言語にとって美とはなにかI』)である。けれど、文学の価値の測定の局面で、むしろ吉本は、両表出をきっちり分けて考えている。言語の指示表出性が言語の「意味」を、言語の自己表出性が言語の「価値」を作り出す。そう考える吉本が、文学的価値の計算において考慮するのは、基本的に後者、自己表出性の反映としての「価値」なのである。だからこそ吉本は、文学作品の評価で、物語性や思想的な内容を重視しない。言語美のモチーフのひとつは、意味内容の次元でみれば取るに足らないような作品の「価値」をすくい上げることにある。
ところが厄介というか、賢明というか、吉本隆明は、「意味」が、すなわち指示表出性が、文学の価値の増加に、まったく関わりがないとも言っていない。「波のうねるように、またうねりがつみかさなるようにおしよせてくる構成の展開」(『定本言語にとって美とはなにかII』)すなわち「指示表出の展開」が、間接的にではあれ、作品の芸術的価値を押し上げると言っている。
この「指示表出」の生み出す波と、やはり作品の時間軸に沿って上下する「自己表出」の波との重なりが、言語表現の総体を形づくる。この二つの異質で、一義的には無関係の波の、数値的に合成されたものが、一作品の芸術的価値となる。中沢新一の言う「複素平面」は、この二つの波の重なりの、一時点における断面のことを指していると考えられる。この平面は、加藤典洋のデカルト平面のX軸を実軸に、Y軸を虚軸に読み替え、時間軸を捨象したとき、ようやく開けてくる平面だ。この平面で、複素数としての言語表現の価値の大きさは、原点から点Aまでの距離によって測られるだろう。そして文学作品の芸術的価値の大きさは、この距離を時間に対して積分することによって得られるはずだ……。
ところが中沢新一は、新潮の追悼文で、先の引用に続けて、こう書いている。
このうちの指示表出の能力は、私たちのような現生人類以前の人間のうちに、すでに獲得されていたことが考えられる。これにたいして、心的空間に自由領域を開く自己表出の能力は、現生人類の脳をまってはじめて出現することとなった。これは指示表出がつくりだす記号的な意味を超えて、意味を増殖させる「価値」の次元をつくり出す。この増殖する価値が、人間の心に過剰を生み出し、自然的秩序からの疎外をもたらしているのである。
太字の強調は引用者による。吉本は、言語美その他の場所で、たしかに「価値の増殖」については語っているが、太字のようなこと、すなわち「意味の増殖」というようなことは、たぶんひとことも言っていないのではないか。
それでは、吉本の言う「価値の増殖」とは、どのようなことか。中沢の、今度は朝日の追悼文から引用してみる。
「これは上着です」と言ったとき、ことばはなにかを「指し示す」働きをしているが、価値の増殖はおこっていない。ところが「これは天使の上着(のよう)です」というときには、価値の増殖がおこって、文学表現の領域に入り込むことになる。
(朝日新聞2012年3月18日付け朝刊)
「これは上着です」と「これは天使の上着(のよう)です」で違いは、だれにとっても明らかだ。後者には前者にない「喩」が組み込まれている。言語美の吉本は、価値を引き上げる修辞のうち、「喩」が最も高度だと考えている。つまり、配点が高い。したがって、吉本の計算法では、「喩」を持つ文は、持たない文より、ほかのすべての要素が同一であることを条件とすれば、価値が高くなる。
このことを、中沢よりも吉本の考えに忠実に言えば、次のようになるだろう。「これは上着です」と「これは天使の上着(のよう)です」とで、「意味」は同じだが「価値」は異なる。「価値」は、「喩」を持つ後者の文で、前者の文よりも、増殖している。
じっさい吉本は、これと同じ言い方を『ハイ・イメージ論』でしている。「(1)彼の眼は真赤だった。」と「(2)彼の眼は兎(の眼)のように真赤だった。」の価値を比べた箇所でだ。
(1)はただ彼の眼が真赤だったことをじかに言表している文だ。(2)は直喩的ないいまわしで、たんに意味をのべるだけなら「兎(の眼)のように」という直喩はいらないはずだ。だが、彼の眼の描写を鮮明にするために、彼の眼の像をひとたび兎の眼の方にちかづけて、真赤だという述意につなげる。この迂回を介して(2)の文章は(1)にくらべて意味はおなじだが価値は増殖される。
(『ハイ・イメージ論』太字強調は引用者)
つまり「価値」は「意味」の増加分ではない。「価値」はあくまで「価値」として増加し、増殖する。吉本はそう考えている。しかし、「価値」と無関係の「意味」も、ある特定の場合に限り、「価値の増殖」に参与できる。それは、自己表出とベクトルの違う指示表出が、自ら方向を異にする力をはらみ、うねり、波形を描く場合である。そのとき無形の「意味」がひとつの修辞形態となり、修辞形態であるからには「価値」に変換されるのである。
最初、中沢の追悼文で、「意味の増殖」を読んだとき、たんに不注意でそう書いているだけだと思った。けれど、新潮の次の号で続き(?)のエッセイを読み、この言い回しには、思想的・理論的な裏付けがあることを知った。ケアレスミスではなかったのだ。
私の考えでは、現生人類以前の人類にはすでに指示機能をそなえた言語が発達しており、そこに新しく生まれた喩の機能が組み込まれて、現生人類の言語ができたと思われます。ニューロンの間に横断的な結合が生まれるような進化が実現された結果、現生人類は重ね合わせから新しい意味を発生させる喩の能力を身につけるようになったことが考えられます。
(「数学と農業 『自然史過程について・2』」新潮2012年6月号)
この「指示機能」が前号の「指示表出の能力」に対応していることは見やすいが、注目したいのは、中沢が、「自己表出の能力」を、吉本と違い、もっぱら「喩の機能」と捉えている点である。「喩の機能」とは、一般的に言って、なにか。それは、ようするに、字義的な「意味」に修辞的な「新しい意味」を重ね合わせることだ。したがって、「喩」において、言語表現の「意味」量は累乗されることになる。中沢は、この累乗のことを「意味の増殖」と呼び、そのことを「価値」として考えている。そのことが、エッセイにより、わかった。
でも、この考え方は、吉本の考え方と同じではない。単純な話、吉本は「価値」を実現するものとして、「喩」だけを考えているわけではないからだ。この違いが、両者に間における、「価値」の単位の違いとして現れている。中沢の考えに従えば、言語表現の「価値」の単位は「意味」であり、「意味」が多ければ「価値」が増えていることになるだろう。けれど吉本は、すでに触れたように、「価値」はあくまで「価値」として増殖すると考え、また「意味」を文学的価値計算に参与させる場合も、それを「価値」に換算することを求めている。「価値」の単位は、同語反復的に、ずっと「価値」のままなのだ。
文学の価値は言語の価値。言語の価値は文学の価値。吉本隆明の「価値」とその計算をめぐる思考は、このように、思いのほか線形的である。「価値」を「意味」で裏張りする加藤典洋と中沢新一の、よき理解者としての曲解は、吉本の線形思考を複線化する。しかし、複線化は複雑化とは違う。
じつは吉本は、言語美以来の自分の「価値」観に、自ら疑義を呈したことがある。中沢が朝日の追悼文で「驚くべき仕事」と呼ぶ『ハイ・イメージ論』の、右に引用した「兎の眼」の話に続けて、吉本はこう言っているのだ。「ところでわたしたちは、こういう自註をくわえながらひとりでに疑問がわきおこるのを感じる。わたし自身でさえそうだから、この文章を読んでいる読者がいたとしたら、なおさら疑念をおぼえるにちがいない」
ここでいわば修辞的に釈明されている価値の増殖の概念は、ほんとは文学(芸術)作品のなかではかくべつ価値の増殖にあたっていないのではないかということだ。(1)の文より、(2)(中略)の文のほうが、おなじ意味をもちながら、その内部で価値の増殖を遂げているというのは、価値形態の概念の範囲内でいえることで、文学(芸術)としての価値と価値増殖の概念はこれとはかかわりないのではないか。ある文学作品の文脈のなかでは、逆に(1)の文章の方が(2)(中略)の文章にくらべて価値の増殖になっているばあいがありうるのではないか。
(『ハイ・イメージ論』)
つまり、ここで、「喩」を文学的価値を高める最高度の修辞だとする言語美の単純で素朴な計算方法が、ついに疑われている。この種の疑いは、それこそ吉本が言語美で「恩恵を受けた」と書くリチャーズが、もう四十年も前に、「綾の多寡と価値の大小を混同してはならない」と注意を喚起していた事実を持ち出すまでもなく、あたりまえの当然のことで、いわば常識に属する。でも、なにをいまさら、と驚いて絶句するのは間違いだ。驚くべきはむしろ、出発点で常識を一顧だにしない、吉本の強靭でフェアな思考力の方だろう。
けれど、さらに続けて、吉本が次のような言葉を書きつけるのは、同じようにフェアな態度と言えるだろうか。
こういう疑問のところで、わたしたちは価値形態がふたつの差異の系列をなしている構造体としての言語という領域をこえて、ただ自己表出のたえまのない波形のインテグレーションをさして、価値とよぶようなべつの領域にはいりこむことになる。ここでは言語は指示表出といえども指示性としての機能によってではなく、自己表出の波形と自己同一性に融合するかぎりで意味をもつことになる。わたしたちはたぶんここの領域で、ある側面では自己表出の普遍性に出遭っており、べつの側面では実体的な差異の系列(指示表出)を喪っていることになる。そしてこの領域の意味するところをほんとうはよくわかっていないのだ。
ただ経験のうえでわたしたちは、文学作品のような芸術的な言語では、はじめに<何を指示するか>という目的と有効性にたいして、対応するような非指示的な言語が目指されていることを知っている。けれどいったん表現された芸術的な言語の内部では、言語が<何を指示するか>ということも、<何を指示するか>にたいして対応する非指示的な言語も、たんに形式的なものになってしまい、価値(自己表出)そのものの自己増殖とその拡張だけがモチーフになってゆく。その芸術的な言語がどんな物語を紡ぎだしていても、物語はそこではたんに形式であって、価値(自己表出)の内部でひそかにどんな持続された形態(波形)によって、自己増殖がはかられているかだけが問題だし、それを読み取ることの感性的な銘記(波形)だけが文学(芸術)上の摂取ということになるといえる。
(同)
初見であれば、きちんと文意を追うのは、まず無理だろう(逆に、このブログの今回の記事を読んだ上で読めば、だいぶ分かると思う)。なぜわざわざ、こんな長ったらしい文章を引用したのか。それは、ここにある幻惑的な言葉の連なりの、理論的内容の乏しさを言うためだ。「よくわからないけれど、とにかく自分の経験に照らして言えば、文学作品で、肝は、指示表出ではなく、自己表出にある。指示表出は、自己表出に融合する限りにおいて、意味を持つ。文学の感銘とは、つまるところ、自己表出の摂取のことだ」。結局、吉本は、言語美の発想の土台を崩しかねない深刻な疑いを抱きながら、そんな疑いなど少しもなかったかのように、ここで言語美の価値論をそのまま語りなおしているだけなのだ。吉本の難解な語り口は、読み手を煙に巻くためなのか? そういう疑いが頭をもたげる。
この疑いは、だれもが主著と認める、当の言語美の方にも自然と伸びていく。『言語にとって美とはなにか』は、主著であるのに、べた褒めする人はあるにせよ、正面から本格的に論じられることは意外と少ない。べた褒めも、それが手放しの賞賛であるのなら、ぜんぜん信用ならない。信用は、精査によってしか、回復しないだろう。この書物を覆い尽くす武骨で美的な言葉の上層をすっかり剥ぎとる。語り口を消す。そこに何が残るか、残らないか。それをちゃんと確かめる。必要な作業だ。
というわけで、『言語にとって美とはなにか』の内容を噛み砕き、わかりやすく解説した文章を書こうと思ってます。タイトルを考え中。「完全読解 吉本隆明『言語にとって美とはなにか』」が第一候補ですが、なんだか竹田青嗣の本みたいになるので、別のにしようかと。
「これでわかる吉本隆明『言語にとって美とはなにか』」
「ざっくりわかる吉本隆明『言語にとって美とはなにか』」
「やりなおし吉本隆明『言語にとって美とはなにか』」
「無理なく続けられる吉本隆明『言語にとって美とはなにか』」
「脳を生かす吉本隆明『言語にとって美とはなにか』」
「成功する吉本隆明『言語にとって美とはなにか』」
まあ、とにかく、例によってパブーで販売しようかと考えてます(パブーは今度PDFの禁則処理に対応したようですね)。
あと、いま「トラデュイール」第4号に掲載する文章を書いているのですが、こちらでも、導入部、「自己表出」「指示表出」の対概念について検討しています。両概念は、じつはそれほど難解ではないのに、なぜかひどく難解に見える。拙論では、まず、その理由を探り、それを「像」の概念に結び付け、そこから話を日本語の方に広げていきます。表題はやはり未定ですが、内容的には、日本語の基礎条件について考えた一連の試論(「翻訳入門」「志賀直哉『国語問題』再考」「言葉は現実に動じない」)につらなるものになる予定。
関連するエントリ:
吉本価値論への批判 - 翻訳論その他
吉本隆明『言語にとって美とはなにか』について - 翻訳論その他